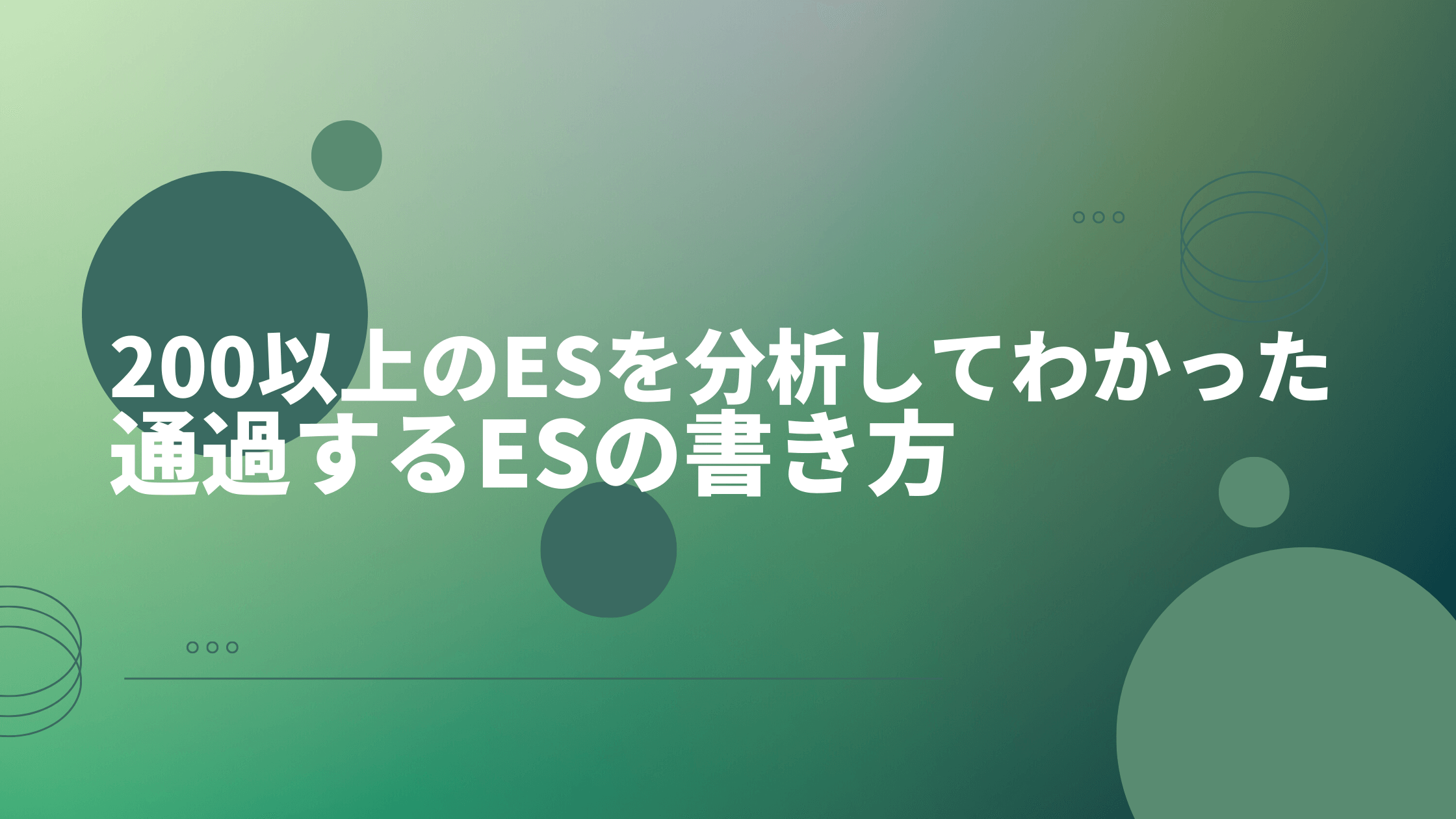選考の結果、不採用とされた場合に届く採用結果通知は「お祈りメール」と呼ばれています。
今回は「お祈りメール」について、その内容や対応方法・立ち直り方、採用されるためのコツなどについて解説します。
Contents
就活のお祈りメールとは不採用通知のこと
「お祈りメール」とは、応募した企業側からメールで届く「不採用通知」のことを指します。
文面の末尾に「今後のご活躍をお祈り申し上げます」と記載されていることが多いため「お祈りメール」と呼ばれています。
お祈りメールの例文として一般的な文面は、以下のとおりです。
件名:【選考結果のご連絡】株式会社〇〇〇
〇〇様
株式会社〇〇〇採用担当の〇〇と申します。
このたびは、多くの企業の中から弊社へご応募頂き、誠にありがとうございました。
厳正なる選考の結果、誠に残念ではございますが、今回は採用を見送らせて頂くこととなりました。ご期待に沿えず大変恐縮ではございますが、ご了承くださいますようにお願い申し上げます。
〇〇様の今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。
このように締めくくられることが一般的です。
就活のお祈りメールに返信は基本不要
お祈りメールが届いた際に、返信すべきか悩むこともあるでしょう。
結論は「返信は不要」です。理由としては、返信してもしなくても、採用可否が変わることは基本的にないためです。
また、企業側は、多くの就活生にお祈りメールを届けているため、返信内容について詳しく確認することはほとんどありません。
お祈りメールに返信する場合の例文
お祈りメールに返信する場合の例文をご紹介します。
株式会社〇〇〇
人事部〇〇様
お世話になっております。
〇月〇日に面接をしていただいた〇〇と申します。
先日は貴重なお時間をありがとうございました。
頂きました選考結果につきましては、誠に残念ではありますが、今回の経験を真摯に受け止め、今後の就職活動に活かして励んでいきたいと考えております。
末筆ながら、今後の貴社のご発展をお祈り申し上げます。
〇〇(氏名)
面接をしていただいたことへのお礼や、就職活動における今後の想いなどを、失礼のないように書きましょう。
約2週間待って連絡が来なければ不採用と考えてよい
面接から約2週間経過しても選考結果のメールが届かないときは、不採用と考えてよいでしょう。
不採用者全員に通知を届ける作業は、時間・人員など、さまざまな労力が奪われるため、人事部の業務や負担を軽減する目的で、不採用通知を届けない場合があります。
この現象は「サイレントお祈り」と呼ばれ、応募者数の増える大企業で実施されることが多いとされています。
採用結果を問い合わせる適切なタイミング
採用結果を問い合わせる適切なタイミングとして、企業側が提示した期日を待った上で、さらにその期日から2週間ほど経っても連絡が来ないときは、問い合わせてもよいといわれています。
採用担当者は多忙であることが予想されるため、なるべくこちら側から問い合わせることは避けた方がよいでしょう。
そのため、面接の際に採用結果の通知がいつ頃なのかについて確認することをおすすめします。
なお、企業側に問い合わせを行う際、採用結果をその場で確認することはマナー違反であるため、いつ頃採用通知を届けていただけるかの確認にとどめておくことが肝心です。
採用結果の時期を確認するためのメールの例
採用結果の通知時期を確認するための、お問い合わせ例文をご紹介します。
件名:面接の結果につきまして/〇〇大学〇〇学部 〇〇
〇〇株式会社採用担当
〇〇様
お世話になっております。
〇〇大学〇〇学部の〇〇です。
先日は面接の機会を賜り、誠にありがとうございました。
〇日までに結果をご連絡いただけると伺ったのですが、
現時点でお返事を頂戴しておりません。
いつ頃ご連絡をいただけるかを、お教えていただくことは
可能でしょうか?
ご多忙の中、大変恐縮ではございますが、何卒よろしくお願い致します。
面接に対する礼や、結果通知の期日を伺っていることなどを、
失礼のないように書きましょう。
就活のお祈りメールからの立ち直り方
就活のお祈りメールが届くと、落ち込んでしまうこともあるでしょう。
ここでは、お祈りメールからの立ち直り方についてご紹介します。
今の自分の気持ちを書き出す
今の自分の気持ちをノートやメモなどに書き出してみましょう。
文字にして書き出すことで、頭や気持ちが整理されるとともに、気分がスッキリします。
気分転換する
スポーツをしたり、映画を見たり、気分転換をするとよいでしょう。
お祈りメールが届いて気分が落ち込んでしまっている状態では、余計なことを考えてしまいよい打開策は浮かばないものです。
気分転換の方法としては、部屋の掃除をしたり映画を見るなどがあります。
体を動かすこともおすすめです。ちょっとした体操や近所の散歩などでも十分効果があります。
深刻に捉えすぎない
また、お祈りメールについてあまり深刻に捉えすぎないことも重要です。
就活とは、自分の努力のみですべてが決まるわけではなく、そのときの運や企業側との相性・タイミングなど、さまざまな影響を受けます。
そのため、自分の能力不足や、力不足を気にして、自分を攻めることはやめましょう。
大切なのは次への準備|就活で採用されるためには
ここまでお祈りメールについて解説してきました。つぎはお祈りメールが届かないように、就活で採用されるためのポイントをご紹介します。
基本的な身だしなみやマナーを守る
基本的な身だしなみやマナーを守ることは、印象をよくする上で重要です。
身だしなみが整っている
頭髪や服装など、身だしなみを整えましょう。見た目が整っていないとだらしないと思われ、面接ではマイナスポイントです。
約束時間を守る
社会人として時間を守ることは、最低限のマナーです。交通機関のトラブルも考えられるため、早め早めに行動をすることが重要です。
挨拶や正しい言葉遣いができる
挨拶や正しい言葉遣いは、マナーの基本です。マナーが守られていないと面接官の印象は悪くなるため気をつけましょう。
相手の話を聞いている
相手の話をしっかりと聞くことは、コミュニケーションの基本中の基本です。面接官の質問を的確に受け止め、しっかりと受け答えをしましょう。
上記4つのポイントを押さえることで、面接官への印象がよくなります。
業界・業種を広げる
自分が望む職業と、自分の能力が合っていない場合があるため、他の業界・業種に視野を広げてみることが大切です。
また、志望業界・業種を絞ってしまうことで、就職先への選択肢が少なくなってしまうこともあります。
特定の業界に限らず、就活フォーラムや企業説明会・講習会に参加したり、OBに相談したりして、さまざまな業界・業種について研究することがおすすめです。
反省点を生かす
選考時の反省点を分析し、ふたたび同じようなことが起きないようにすることも、採用されるためのポイントです。
たとえば面接で上手くいかなかった場合には、次のような点について振り返ってみましょう。
面接での自分のふるまい
受け答えの表情が柔和だったか
面接官からの問いかけに対して簡潔に分かりやすく話せていたか
的外れのことを面接官に質問していないか
失敗を活かし、次につなげることが重要です。
面接の練習をする
面接を上手く行うためには、慣れることが大切です。
面接に慣れていれば、どのような質問に対しても、あわてず的確に回答できます。
面接の練習をする際には、実戦に近い練習となるように心掛けることが大切です。
例えば、学校内で集団面接・個人面接などの模擬面接を行える環境があります。
面接練習を積み重ねることで、本番の面接では自信を持って受け答えできるようになるでしょう。
まとめ
お祈りメールが届いたときは、スポーツや映画など、気分転換をすることがポイントです。
立ち直った後は、次こそ採用されるために、反省点を活かす・面接練習を積み重ねるなど、就職活動に向けての行動が大切です。
就活でお祈りメールが届いた場合には、立ち直り方や、企業側への問い合わせ方法など、ぜひ今回の記事をお役立てください。